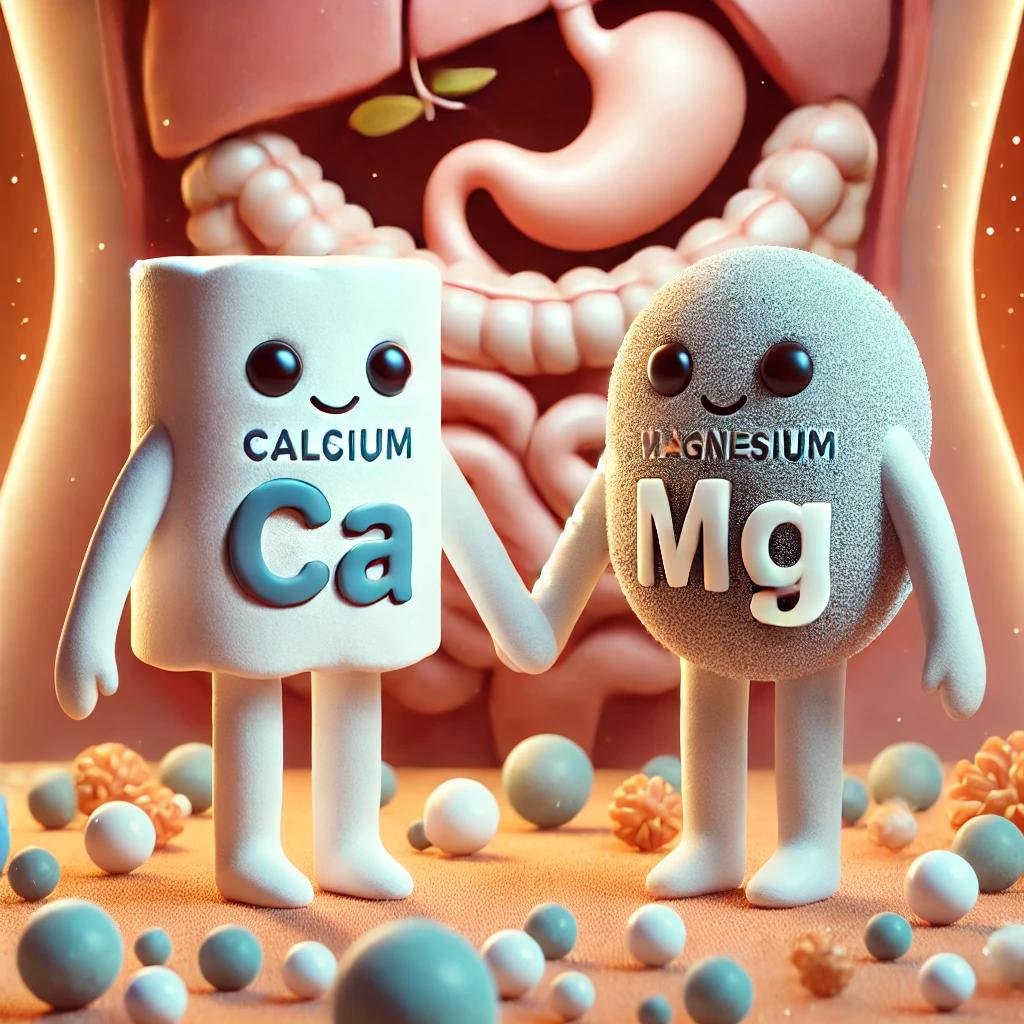カルシウム摂取の注意点
〜善玉?悪玉?知っておきたい重要な役割〜
カルシウムは「骨や歯を強くするミネラル」としてよく知られていますが、それだけではありません。
マグネシウムと密接な関係を持ち、体内のさまざまな機能を支える重要な栄養素です。
しかし、カルシウムには「善玉」と「悪玉」が存在し、摂り方を間違えると健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
今回は、カルシウムの重要な働き、「善玉」と「悪玉」の違い、効果的な摂取方法について解説していきます。
① カルシウムの役割とは?
カルシウムは体内でさまざまな役割を担っています。
✅ 骨や歯の形成
• 体内のカルシウムの99%は骨や歯に蓄えられ、丈夫な構造を作る
✅ 残りの1%は、血液や細胞に存在し、重要な機能を果たす
• 心臓の鼓動を安定させる
• 神経の信号を筋肉へと伝達し、適切な収縮をサポート
• 免疫の調整を行い、白血球の働きを助ける
✅ 筋肉の収縮と神経の伝達
• マグネシウムとバランスをとりながら、筋肉の動きや神経の興奮を調整(※相反する動きで連携し、アクセルの役割を果たす)
✅ 血液の凝固作用
• 出血した際に血液を固め、止血を助ける
✅ ホルモン分泌の調整
• 副甲状腺ホルモンと連携して血中カルシウム濃度を一定に保つ
✅ DNAの安定化と免疫のサポート
• 細胞分裂を正常に行うために必要な酵素の働きを支え、アポトーシス(不要な細胞の死滅)を促進
• 免疫機能を維持し、感染症や炎症のコントロールに関与
このように、カルシウムは骨の材料としてだけでなく、筋肉・神経・血液・免疫など多くの生命活動に必要なミネラルです。
② 善玉カルシウムと悪玉カルシウムの違い
善玉カルシウム(体に必要な形で吸収されるカルシウム)
• 食事由来のカルシウム(魚・海藻・緑黄色野菜)
• 骨や歯の形成に使われるカルシウム
• 体内で適切に利用され、骨や歯、筋肉の働きを正常に保つ
悪玉カルシウム(体に不要に蓄積されるカルシウム)
• カルシウム過剰摂取(特にサプリメント由来)
• イオン化されたカルシウムサプリや乳製品に多く含まれ、体内での吸収が早すぎるため、骨や歯に届く前に血管や臓器に沈着しやすい
• 動脈や腎臓、関節に蓄積し、石灰化を引き起こす
➡ 悪玉カルシウムは、血管や腎臓に沈着し、動脈硬化や腎結石のリスクを高めることが知られています。
特にサプリメント由来のカルシウムは、過剰摂取によって体内のバランスを崩し、かえって健康に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
③ 効果的なカルシウムの摂取方法と注意点
✅ 食品から摂取する
カルシウムは、できるだけ自然な食材から摂ることが理想的です。
カルシウムを多く含む食品
• 魚介類(いわし・しらす・干しエビ)
• 海藻類(青さ・わかめ・昆布)
• 緑黄色野菜(小松菜・チンゲン菜・水菜)
✅ カルシウムの吸収を助ける栄養素を組み合わせる
• ビタミンD(魚類・きのこ類) ➡ カルシウムの腸での吸収を促進
• ビタミンK2(納豆・発酵食品) ➡ カルシウムを骨に運ぶのを助ける
• マグネシウム(海藻・ナッツ) ➡ カルシウムの適切なバランスをサポート
✅ カルシウムとマグネシウムのバランスを考える
• カルシウムとマグネシウムは2:1の割合で摂取するのが理想的
• マグネシウムが不足すると、カルシウムが適切に代謝されず、血管や腎臓に沈着しやすくなる
✅ 乳製品の摂取はほどほどに!
• 乳製品の摂取量が多いと、マグネシウム不足を引き起こす可能性がある
• 特にチーズは体内でのマグネシウム消費を促す
⚠ 過剰摂取に注意
カルシウムを過剰に摂ると、マグネシウム不足や石灰化のリスクが高まるため、適量を意識することが大切です。
④ 私の体験談
私はもともとチーズが大好きで、毎日たくさん食べていました。
しかし、カルシウムとマグネシウムのバランスについて学んでから、チーズの摂取を控えるようにしました。
すると、日中の疲労感が少し軽減したように感じています。
カルシウムは重要なミネラルですが、過剰摂取や摂り方によっては、体に悪影響を及ぼすこともあります。
マグネシウムとのバランスを意識しながら、食事から適量を摂ることが大切です。
皆さんも、カルシウムとマグネシウムの摂取バランスを意識してみてはいかがでしょうか?
過去の記事はこちら
医療免責事項
⚠ 本記事の情報は一般的な知識の提供を目的としており、医学的アドバイスに代わるものではありません。
⚠ サプリメントの摂取や栄養摂取について不安や疑問が
ある場合は、必ず医師や栄養士にご相談ください。